

平素よりTSUTAYA TVをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
TSUTAYA TVは2022年6月14日(火)をもちましてサービスを終了致しました。
今までご愛顧いただきましたお客様には厚く御礼申し上げます。
引き続きTSUTAYAのサービスをご利用いただけますことを心よりお待ち申し上げております。
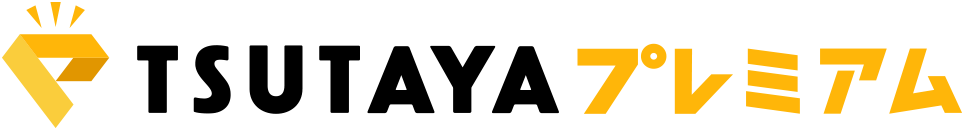
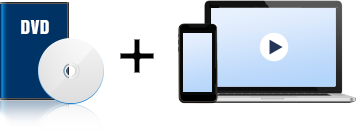
月額1,100円(税込)のTSUTAYAプレミアムにお申込みいただくと、TSUTAYA店舗の旧作DVD借り放題とdTVの動画配信をご利用いただけます。


DVD・CDの取り扱い作品数国内最大級の宅配レンタルサービスです。 観たい・聴きたい作品を1枚からレンタル可能。おすすめの定額プランもご用意しております。